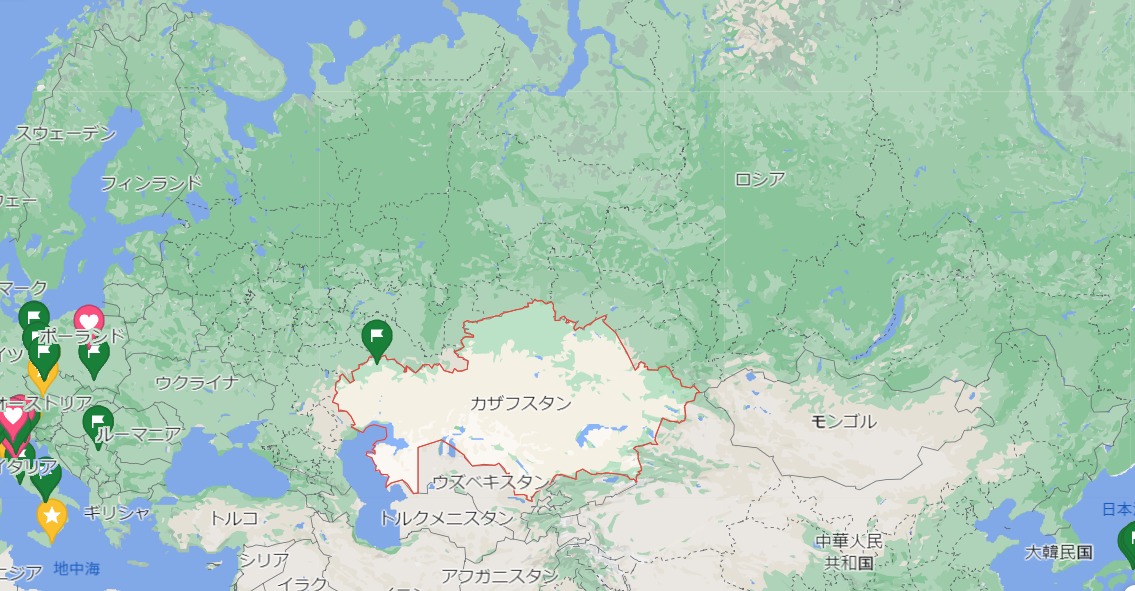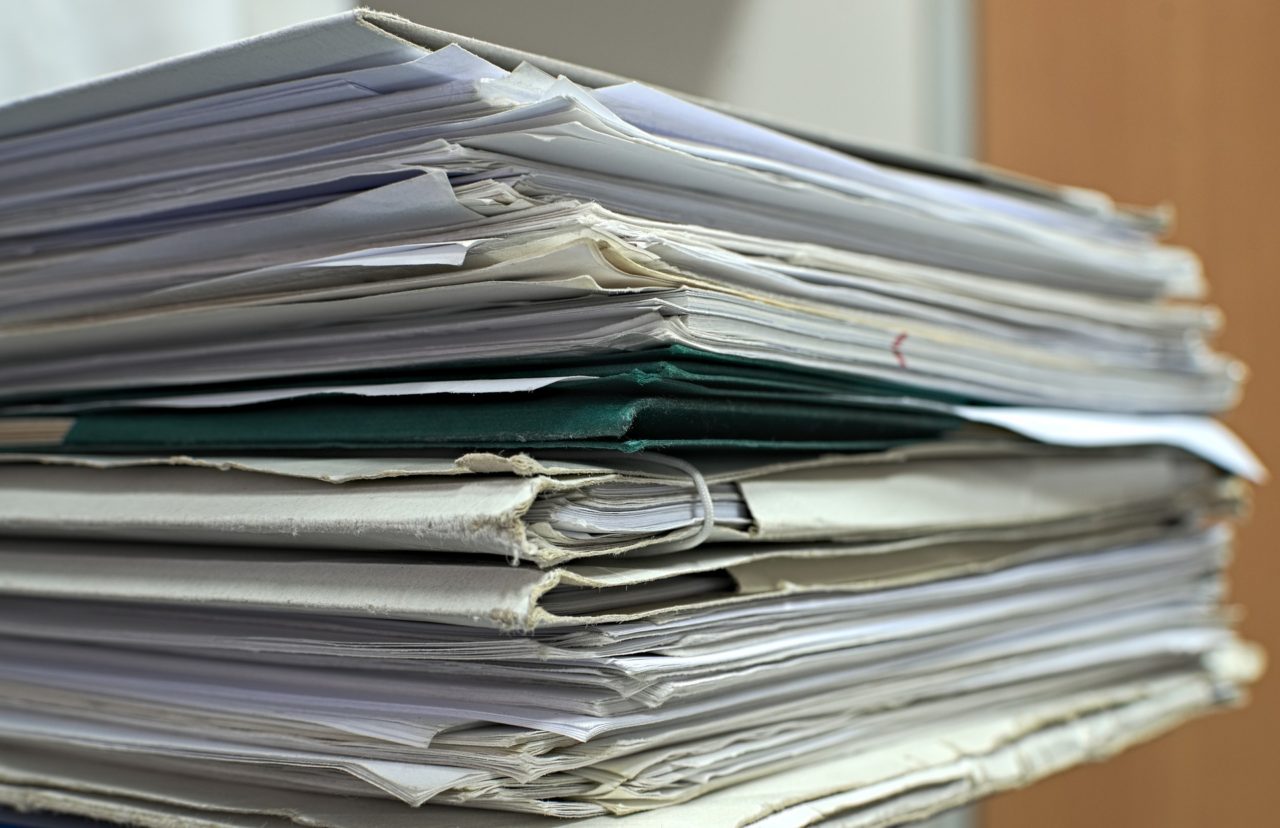【Twitter】https://twitter.com/PROGRESSrie
【自己紹介動画】https://www.facebook.com/groups/282970169246035/posts/874708956738817
こんにちは!
イタリア語で好きなフレーズは「Puoi fare quello che vuoi.」、
「君はやりたいことをすることができる」というフレーズの、桜井リエです。
2021年8月に世界初学費無料・非営利・世界初出願から卒業まで完全オンラインのアメリカの大学「University of the People(UoPeople)」を修了し、
在学中にYouTube大学を1年以上観ていた中で自分を変えるきっかけがほしいなと思い、10月にPROGRESSに入会しました。
詳しい事は自己紹介動画で紹介しているので良かったらご覧ください。
あっちゃんがZ世代の授業をしてくれてから、毎日ラウンジで全ての世代の方とお話しし、「国によってZ世代の特徴は違う」という気づきを得ました。
【記事の内容】
このコラムシリーズでは、私が住んでいたカザフスタン、アメリカ、チェコ、フランス、イタリアの国別で「国によって起きているデジタル格差」、
そして「文化の違いによるZ世代の環境・社会問題への意識の違い」について私自身の経験談からお伝えできたらと思います。
全てを1記事にまとめると長くなるので、国別で記事を分けて書きます。
もし、この記事が好評であれば今後のコラムシリーズをさらに書きたいと思っているので、記事が「面白い!」と思った方は記事下にあるTwitterでの「シェア」、「いいね」を押してくださるととっても嬉しいです!
【結論】
お金持ちの国ではデジタル化が進んでいる。先進国でデジタル化が遅いのは日本だけ。環境問題への意識が1番高いのはヨーロッパ。各国の共通点は以下:
- ダイバーシティやインクルーシブを重視
- SNSの利用頻度が高い
- デジタルネイティブ
- 留学は身近なもの
※私が住んでいた国ベースでお話するので、必ずしも私の意見が合っているとは限らないため、参考程度に読んで下さい。
そして、もう1つ伝えたいのが、Z世代といっても「人によって」違うということです。
私は1997年生まれですが
・3才からメアド作成
・3才で「あいうえお」ソフトで50音を覚えた
・3才からパソコンで1人で検索してゲームを見つけていた
・パソコンと携帯は小学校4年生から
・小学校4年生にYahooブログ開設
・アメリカ留学中(2016年)の生活資金は日本からビットコイン送金でドルを入手
等幼いころから最新のテクノロジーに触れていましたが、同世代で同じくらいデジタルネイティブの人はいませんでした。
家の環境も特殊で、ロシア語がネイティブの住み込みの家政婦さんが日本でいたので家ではロシア語の環境が整っていましたし、母の友人は旧ソ連圏の人や中東の人がよく家に遊びに来ていたので、日本にいながらもかなり国際的な環境で育ちました。
同世代の帰国子女の友達も
・フランスの現地校に5年以上通っていたのに日本語がぺらぺら
・オーストラリアに10年以上現地校に通い、日本語学校に通うものの日本語は小学生レベル
・慶應義塾ニューヨーク学院に通っていたけれど、友達が日本人ばかりで日本語の方がぺらぺら
というような感じで、私の周りの同世代でも1人1人が全員違う環境で育っています。
【カザフスタン】
始めに軽くカザフスタンの紹介をさせて下さい!
最近ZOZOTOWNの創業者である前澤さんはカザフスタンのバイコヌールから宇宙に行きました!
そして、カザフスタンでは内戦はありません(笑)
よくパキスタンやアフガニスタンと間違える人がいますが、
カザフスタンには約130以上の民族がいると言われているのにもかかわらず紛争がない珍しい国です。
さらにカザフスタンは地下資源が豊富な国であり、コトバンクによれば
・西部のカスピ海北東岸地帯は鉄、石炭、燐(りん)鉱、石油、天然ガスなどの有用鉱物に富む
・2009年の石油埋蔵量は398億バレル(世界の3.2%)、天然ガス埋蔵量は1兆8200億立方メートル(世界の1.0%)
・ウラン、クロム、燐鉱石の埋蔵量は世界第2位、亜鉛の埋蔵量は世界第5位となっており、ベリリウム、タンタル、チタン、タングステン、アルミニウムなども世界有数の埋蔵量
があります。
質が良い馬肉も有名ですし、私の母の出身地はキャビアを輸出しています。
この様に、資源に溢れているので旧ソ連諸国の中でもお金持ちが多い国として知られています。
実際私のカザフ人の同級生はプライベートジェットを持っている人が多いです。
ちなみに、今世界で一世風靡している世界的人気歌手のDimash Kudaibergen(ディマシュ・クダイベルゲン)もカザフスタン出身です!
紙の辞書からiPhoneへ
まだまだ物足りないですが、ここからカザフスタンと日本で経験したデジタル格差についてお話しします。
私は幼稚園から中学校1年生まで日本にいて、中学校2年生の時に父の仕事の都合でカザフスタンに2011年から3年間駐在する事になりました。
私の母はカザフスタン出身で、私が生まれた頃からロシア語で私に話しかけていたので
日本にいながらも家ではロシア語、学校では日本語という環境でした。
そのため、カザフスタン渡航後は英語力がゼロで、
「ハロー、マイネーム、イズ、リエ。アイム、サーティーン。」しか言えなく、
なんと現地のインターに英語があまりにもできなさすぎて入学を断られました(笑)
そのため雇ったチューターの先生に「ロシア語で英語を教えてもらう」という状況に陥り
私はロシア語は理解できたけれど勉強したことがなかったのでレッスンでは
「ロシア語→日本語」+「英語→日本語」の2つの分厚い紙の辞書を使っていました。
日常会話が少しできた段階でアメリカンインターナショナルスクールのサマースクールに行き、そこで衝撃の事件が起きたのです。
生徒は毎日変わり、10人程の構成で8割が韓国人、残りはカザフ人やその他の国の生徒。
紙の辞書を使っていたのはいつも私だけ!
先生からロシア語でも教えてもらうために6kg相当のロシア語と日本語の辞書を抱え、当然単語を調べる時間も私だけ遅いので授業に全くついていけなかったのです。
私以外の生徒は全員iPhoneアプリの辞書を使って単語を調べているのを見て、
サマースクール1週間後には、父親に「iPhoneがないと生き延びられない!」とお願いし、紙の辞書から卒業しました。
他にも、カザフのインターでは
・幼稚園生から授業でタブレットを駆使
・小学生でパワポを使ったプレゼンは当たり前
・パソコンを使ってWordでエッセーの作成
・卒業アルバム(Year Book)は写真撮影・Photoshopでの編集・Adobeで表紙デザイン作成等を全て生徒が担当
・図書室にはMicrosoft Officeの使い方やエッセーのフォーマットを教えてくれる先生が常駐
・心理カウンセラーと進路相談のプロも常駐
・授業もスクリーン・パワポ・参加型
・授業ごとに自分の勉強進行具合をデータ化して見せてくれる
・部活動は必要であればプロの先生を雇いセミナーを開く
全てが最新の状態を保ったインターに通っていたので、生徒一人ひとりがパソコンを持っていましたし(エッセーを書くため)、スマホももちろん1人1台持っていました。
さらに、中学校3年生の夏休みの間にオンラインコースをPearsonで数学の授業を取り、単位移行をすることができていたので、それが「当たり前」にできる環境に世界はなったんだと勘違いしていました。
【日本の高校に編入】
駐在が終わり、高校2年生の9月編入という特別枠で帰国子女が多い日本の高校に編入しましたがカルチャーショックが大きすぎて1日でも早く海外に出たいという思いが在学中は強かったです。
日本の高校では
・授業は黒板
・パソコンを授業中に開いてはダメ
・オンラインコースを取って単位移行ができるシステムがなかったので、事前に勉強する事が出来なくて習ったことがない「古典」「漢文」を高校2年生レベルのものを求められる
・数学のカリキュラムもアメリカと違って日本の方が2,3年早かったため、数Ⅰを習い始めたばかりたったのに、急に数ⅡBの空間ベクトルから授業が始まりちんぷんかん
・1日の終りに大量の紙のチラシやお知らせが配られる
・Microsoft Officeをしっかり教えてくれる先生が常駐していない
・部活動の先生は雇われておらず、教職員が教えていた
・授業中に生徒は発言せずに参加型ではなかったので、自分の意見を発言する機会がない
生徒も日本人だけだったので、なんだか急に世界が狭くなった様に感じました。
そして、何よりも日本では「オンラインコース」を取って「単位移行」するというシステムが小・中・高にはなく、
高校2年生の9月編入の私は皆さんが想像できない位の苦労をしてなんとか合格点を取っていました。
日本語のオンラインコースのシステムさえあったら、カザフスタンにいる間に足りない知識を勉強することができて、日本の高校の授業にも問題なく追いつけたはずです。
その高校をなんとか私は卒業する事ができ、アメリカのウィスコンシン州のリベラルアーツ大学に進学することになるのです。
次回続きは「アメリカ編」となっております 🙂
「続きが読みたい!」と思ってくださったあなた!
記事下にあるTwitterでの「シェア」、「いいね」を押してくださると次の記事を書くモチベーションになり、私、桜井リエが嬉しくなります!(笑)

 27いいね!
27いいね!